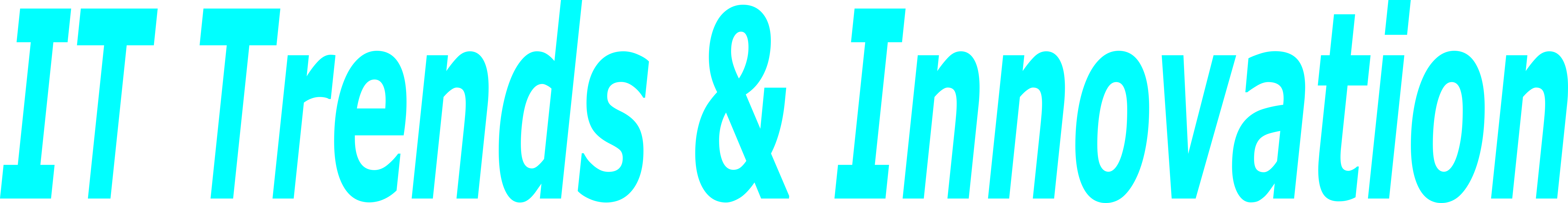
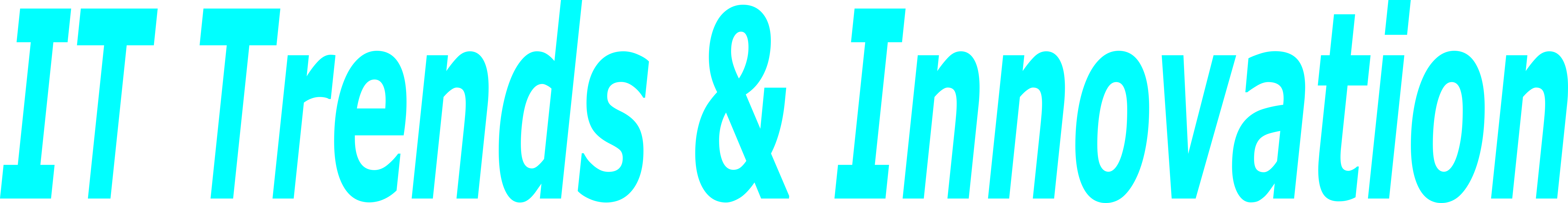
Source: MSN News, 2025年7月21日

日本の半導体復活を託されたラピダスは、需要の見通しがないまま巨大投資に踏み切ってしまった。日経新聞記者として半導体業界に詳しい筆者の見立てでは、このままでは「日の丸ファウンドリー」の成功は極めて怪しいという。日本には日本の強みを生かせる別の道があったにもかかわらず、戦略なき政治主導が道を誤らせた。いま求められているのは、現実に即した勝てるビジネスモデルだ。エルピーダ社長を務めた故・坂本幸雄が語った、日本半導体の逆転の一手とは?※本稿は、小柳建彦『ニッポン半導体復活の条件 異能の経営者 坂本幸雄の遺訓』の一部を抜粋・編集したものです。
安易な「垂直統合」モデル放棄が
日本半導体を沈めてしまった
微細加工技術とその量産化能力で韓国・台湾・日本が米国に対して優位性を持つという事実は、日本の半導体業界にあることを暗示している。
ニッポン半導体の凋落の大きな要因は、設計と製造を別々の企業が分担する分業モデルの波に乗り遅れことだと長年語られてきた。しかし、日本的雇用慣行、日本人の製造現場での「カイゼン(編集部注/トヨタが考案した業務改善手法。ムダを排除し、より効率的で生産性の高い状態を目指す)」の得意さ、などを考えると、製造プロセス技術を強みにできるIDM(設計から製造まで自社で手掛ける半導体事業)モデルを追求しながら的を絞った製品戦略を築いていれば、日本の半導体産業にはまた別の道が開けたのではないかという「たられば」の可能性だ。
実際、メモリー半導体ではDRAMもNANDフラッシュも、日本という立地でIDMの勝負ができている。仮に、ロジック半導体で1つでも日本のメーカーが大きな戦略分野を探りあてれば、IDM型の先端ロジック半導体企業が育った可能性があったのではないだろうか。
東芝はしばらく、エルピーダのDRAMと自社のNANDフラッシュを貼り合わせて、携帯端末向けの省電力・薄型メモリーモジュールを作って売っていた。さらにCPUを含むロジック半導体のノウハウもあった。「たられば」を重ねることになるが、NANDフラッシュに加えてロジックとDRAMをそろえてあれば、サムスン並みのスマホ向けのSoC市場の一角をIDMモデルで取れたかもしれない。
もっと言うなら、東芝は家電も個人向けノートパソコンも世界に売っていた。スマホそのものでも勝負できる技術や人材、販路を持っていたはずだ。そうすれば、もともと日本の総合電機が得意だった垂直統合モデルでスマホ市場にも食い込めたかもしれない。SoC(編集部注/コンピューターの頭脳にあたる機能を1つのチップにまとめたもの。スマホや自動車などの電子機器に使われる)にしろスマホにしろ、ビジネスモデル思考の欠如と、リスクをひたすら嫌がる経営層の間違った思考回路がもたらした機会損失に思えてならない。
コツコツ型人間が多い日本は
本来ファウンドリーに向いている
もう1つは、ファウンドリーの可能性である。坂本の言う、日々コツコツ型の微細プロセス技術開発に日本人が強いことは、すでにメモリー半導体で実証済みだ。
仮にロジック半導体もそういう世界になっているとすれば、理屈のうえではTSMCに伍せるファウンドリー事業の確立も可能性があるとみてよいだろう。だからこそ、Rapidus(ラピダス)(編集部注/北海道千歳市にある、技術レベルはTSMCの最新工場に比肩し得る先端半導体向けファウンドリーを目指す国内企業)はそこに挑もうとしている。
1つ注意したいのは、サムスンのファウンドリー事業が、彼らの望むほどには成長していないという事実だ。
坂本があるとき、当時サムスンの半導体部門のトップでその後グループCEOとなる李潤雨と食事をした際、サムスンのファウンドリー事業が大きくなるにはどうしたらいいかという議論になった。
坂本は「サムスンという看板を外さないと、お客さんと競合してしまうので上手くいかないのではないか」と指摘し、李も同意して頷いていたという。何年か後に再会し何も変わっていない点を突っ込むと、「グループの方針でサムスンの看板は外せない」と弁解したという。
坂本はこう解説した。
「純粋ファウンドリーであるTSMCや聯華電子(UMC)には、製品企画段階から顧客企業が相談に来ます。設計の部分も含めて相談します。しかし、サムスンのように自分でロジック半導体もスマホ端末もテレビも作って売っている会社にそのようなアイデア段階の話を相談すると、そのアイデアを利用されるのではないかという不安がどうしても付きまといます。いくらファイアウオール(編集部注/グループ会社間での顧客情報の共有を制限する規制)があると言い張っても、抵抗があるでしょう。やはりファウンドリーでマーケットを取るならTSMCのような中立性が大事です」
今見えるラピダス最大の強みは
顧客と競合しない「中立性」
これはインテルのファウンドリー事業も共通して抱える問題だ。プロセッサーを本業とするクアルコムのようなファブレスメーカーはインテルに新製品の仕事を頼みにくい。
逆に言うと最終製品も自社製ロジック半導体も持たないラピダスは、先端微細回路の量産と、それに最適な設計を請け負える体制を整えられれば、中立性を武器にファウンドリー市場でプレゼンスを確立できる可能性がある。
ただ、自社や国内の需要が乏しいまま、最初から高い設備稼働率を実現するだけの受注を取れるのかという素朴な疑問が、ラピダス構想には最初から横たわっている。
「日本には先端ロジック半導体のファブレスメーカーがありません。スマホの大手もない。先端半導体を必要とする最終製品がないのです。そこをどうするかが、日本の課題でしょう」
このような話をしていると、やはり肝心なのは製品とビジネスモデルの開発のところだ、という議論に坂本は立ち戻った。
「例えば日本が強いのは自動車でしょう。これから電動化と自動運転化で自動車のパラダイム転換が起きていくときに、肝心の自動運転AIのソフトとハードを押さえないで、どうやって世界で戦っていくのか。僕ならその辺りの課題をとっかかりにロジック半導体のビジネスモデルを考えていくと思います。自動車メーカーは自動運転に必要なデータも大量にためているはずです。うまく活用すれば、自動運転AI向けの新しい車載半導体とソフトウエアの大きな需要を掘り起こせるはずです」
「バラバラのままでは勝てない」
坂本幸雄が残した集約による逆転策
もう1つ、坂本が日本の電機業界に言い残したのは、日本が強い半導体品種を集約して世界のトップシェアを取るべきだという話だ。
「日本企業のディスクリート(紀男注:Discreteは Continuousの反対語で不連続)(編集部注/単一機能の半導体。信号増幅などに使うトランジスタ、電流を一方向に流すダイオードなどがある)の世界シェアは全部合わせると25%になります。集約してブランド強化すればもっとシェアが取れる。仮に4割、5割取れれば、安定した高収益企業になります」
「日本のアナログ半導体も10社超で世界の13%のシェアを分け合っています。1社か2社に集約して開発と設備に投資すれば、もっと高い世界シェアを確保できるはずです。経済産業省は、どうせならそういうところで国の戦略としてリーダーシップを発揮すればいいと思います。各社に構想に乗るかどうか決断を迫る。ちゃんとしたCEOを付けて、株をもたせて、成功したらちゃんとキャピタルゲインが入るようにすれば、やる気を出して経営を引き受ける人材も出てくるでしょう」
1980年代から日本の電機業界をつぶさにウオッチし、2020年から坂本を自分の主催する「技術経営(MOT)」専攻コースの客員教授に招聘した東京理科大学教授(2025年4月から熊本大学卓越教授・立命館大学名誉教授に就任予定)の若林秀樹は、「何かの製品や事業の話をするときに、最初からビジネスモデルとセットで語れる坂本さんのような思考回路がないと、テクノロジー企業の経営は難しい」と指摘する。
エヌビディアは、通常のコンピューターのCPUが色々な計算や処理を柔軟にこなせる一方で、多数の計算を並列処理することが苦手なことに目を付け、大量並列処理が求められる画像処理専用の半導体の市場を作り出した。
その延長線で、大量の行列計算を並列に高速処理する必要があるAI向けにもGPUが役に立つという発想につながった。マーケティング思考からビジネスモデルの形成につなげた成果だ。
SoC市場で日本は復活するか?
日本企業3社の挑戦が始まる
現在、上位10番目前後で活躍するファブレスの台湾のメディアテックはUMCが顧客のために設計部分も受託できるように作った一部門から始まった。ストレージ機器やデジタルテレビなどで、異なるメーカーが似たような仕様のチップセットを求めることに気付き、自らメーカーとなって標準化した用途別半導体を売ろうというビジネスモデルに行き着いた。そこからスマホ向けアプリケーションプロセッサーを核とするSoC(紀男注:System on Chip)への需要を捉えて大きく成長した。アンドロイドOSをグーグルが無償公開したことで中国、韓国、日本などにスマホメーカーが多数誕生したからだ。今ではTSMCの大口顧客である。
米国ではアップルだけでなく、グーグルやアマゾン・ドット・コム、メタといった巨大IT企業が自らの半導体を企画・設計するようになっている。その結果、彼らの設計を製造できる回路設計に落とし込む設計受託や、その先の量産段階のコンサルティングや設計受託など、受託ビジネスの新たな需要が広がりつつある。
ラピダスやソシオネクスト(編集部注/パナソニックと富士通の半導体設計部門を統合して発足したSoCの設計・開発および販売を事業とするグローバル企業)、ルネサスエレクトロニクス(編集部注/自動車や家電向けに、SoCの半導体を作る日本の大手メーカー)は、AIを軸として急速に立ち上がろうとしている新たな半導体ビジネスの需要をどうつかまえるのか。
ソシオネクストは日本版メディアテックに脱皮できるのか。それとも新しいファブレスの雄を育てるべきなのか。いずれにせよ、工場ができても作るものがなければ意味がない。
インテルすら見落としてしまった
「次」を勝ち抜くビジネスモデルは?
勝てるビジネスモデルは常に変化する。インテルがまさにその変化に苦しんでいる。そして、川上の半導体からスマホなどの最終製品までの垂直統合経営で一時は無敵にさえ見えたサムスンも、半導体の収益力と技術競争力が落ちてきて、1990年代以来の経営の岐路に差し掛かかっている。
坂本が繰り返したスピード経営の大事さ、市場と組織の現場に直結した情報収集に基づくビジョンの頻繁なアップデートの大事さが、ますます増しているといえる。若林は経営者としての坂本を高く評価している。
「坂本さんは独特な毒舌のため、異色の経営者などと呼ばれましたが、意思決定のスピード重視とか、必要な設備投資はきちんとやるとか、フラットな組織とか、実践したことも唱えたことも極めてオーソドックスな経営の王道を行くものでした。逆にそれを異端視してしまう多くの日本の大手電機の経営層の方にこそ問題があったと思います」
そのうえで若林はこう期待を込める。
「日本の半導体産業は今度こそ、技術トレンドの先を見据えたビジネスモデル思考で、先手を打って攻める経営をやってほしい」
若林の期待は坂本が残した言葉と共鳴する。一敗地にまみれたニッポン半導体の復興。それに向けて動き出した人々は今こそ耳を傾けるべきだろう。