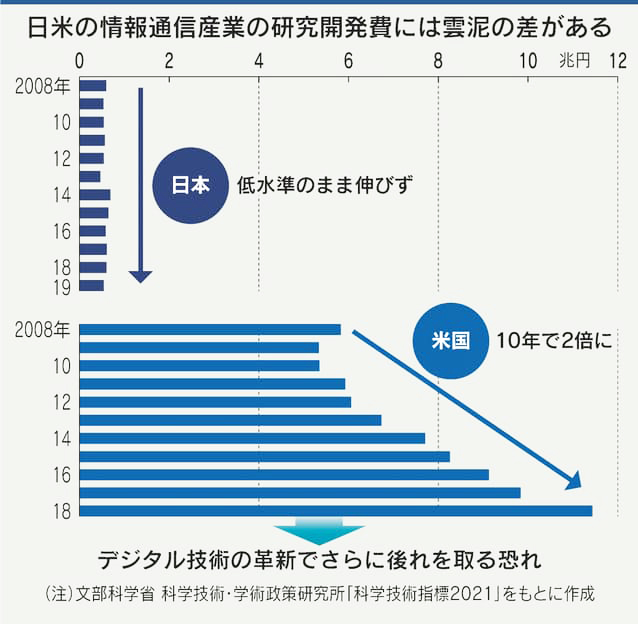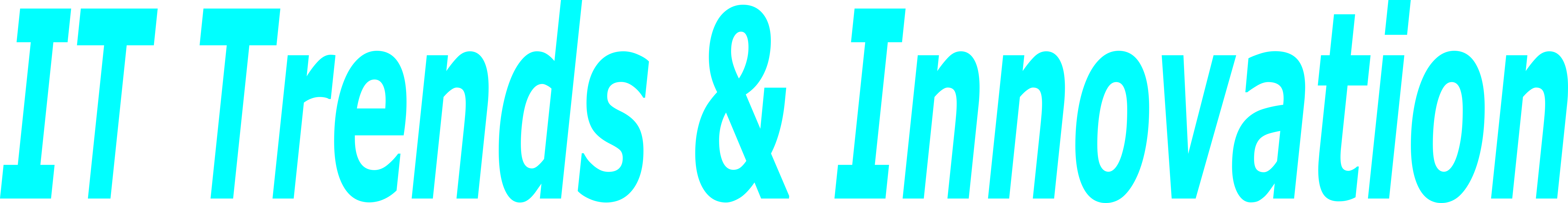
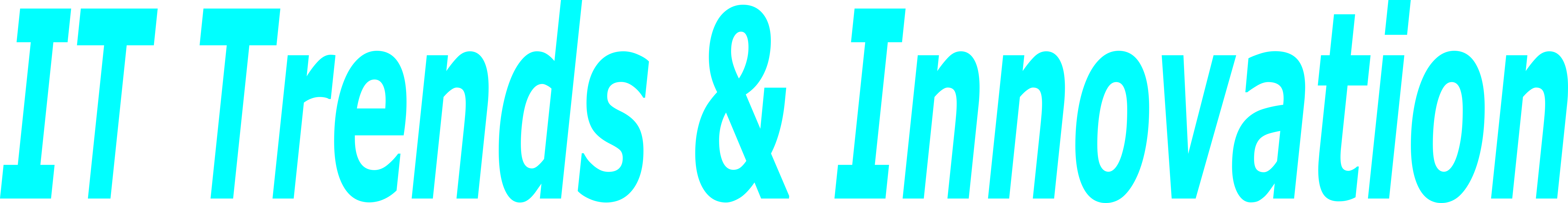
Source: Nikkei Online, 2021年11月8日 2:00
世界の企業がデジタル対応を急ぐなかで、日本の足踏みが目立つ。アップルなど米IT(情報技術)大手5社の時価総額は東証1部の合計を上回る。差はどこでついたのか。日本企業にまだ勢いがあった2000年代、当時は新興企業だった米グーグルで働くことを選んだ日本人社員らへの取材から20年に及ぶ「デジタル敗戦」の要因を探った。
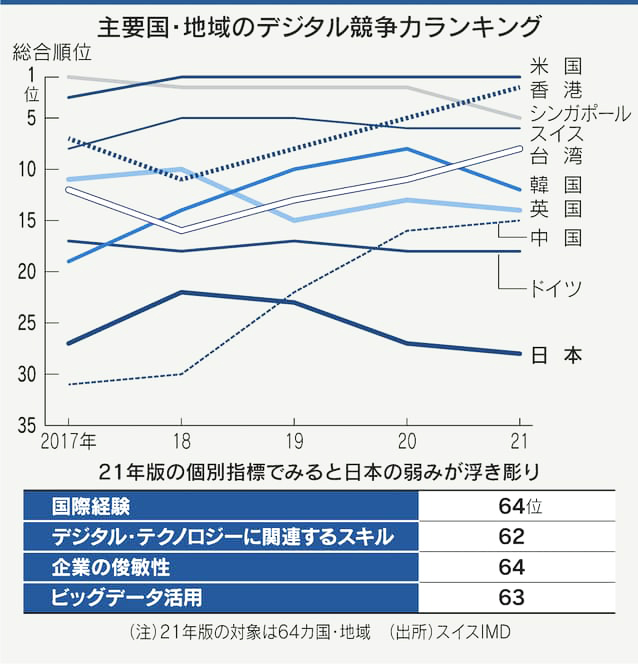
「目の前に座っている人の頭が自分の 3~4倍の速さで回転しているのがわかった」。グーグルの米本社で検索担当ディレクターを務める徳生健太郎氏(03年入社)は、約20年前に受けた入社面接のことを鮮明に覚えている。
徳生氏は米スタンフォード大の修士号を持つ。シリコンバレーの複数のスタートアップに勤務したがITバブル崩壊で職にあぶれ「勢いのついている会社で働きたい」とグーグルに行き着いた。
まだ社員1千人ほどの若い会社だったが、面接を経るうちにすぐに同社が想像をしのぐ「頭脳集団」だと理解した。鋭い質問と次々に展開する話題。自分が入社したら「下の中ぐらいの人間」になると思ったという。
徳生氏の最終面接の相手は共同創業者の一人、ラリー・ペイジ氏だった。「グーグル検索で(改良のために)何をするか」「最近見たクールな製品は」。やりとりは刺激にあふれ、震えるような興奮を覚えながら帰路についた。
徳生氏は同社の競争力の源泉は「個々人が自分で開拓していく」姿勢にあり、それを実践する人材がそろっていたことを指摘する。組織や資金の力で勝負する企業が多かったなか、グーグルは国籍や人種を問わずにすぐにプロジェクトにかかわれるような有能なメンバーをかき集めていた。
多様な人材をいかす組織の仕組みも不可欠だ。06年にNTTコミュニケーション科学基礎研究所から転身したソフトウエアエンジニアの賀沢秀人氏によれば、社員を「のびのびさせながら、同じ方向に進ませる」。
賀沢氏が入社後に「一番ショックというか、驚いた」のは「みんなズケズケものを言う」ことだった。役職や年齢、性別は関係ない。フラットな社風は革新を生む原動力でもあった。手軽に使えるメールサービス「Gメール」は現場の社員が発想し、利用者の使い勝手の良さを追い求めて実現した一例だ。
軸となるのは「どうユーザーに価値を与えていくか」(徳生氏)。各自がバラバラに理想を追い求めることを是とするわけではなく、良いものを作れば売れる、という供給者目線とは一線を画す。利用者が求めるものをデータなどから探り、それを実現してきた。
日本はかつてトップダウン型の統制の取れた組織で製造業を中心に発展し、成長を遂げた。一方、デジタル時代はイノベーションを生む「知の集積」がものをいう。人材と組織に加えて、関係者が口をそろえるグーグルの特徴がスピード感だ。
「どんどんやっちゃうんだ……」。06年に富士通研究所から入社した技術開発本部長の後藤正徳氏は入社以来、地図アプリ「グーグルマップ」の様々な機能の開発をけん引してきた。初期のころに驚かされたのが、サービス展開の速さだった。
05年に「ベータ版」として登場したグーグルマップが表示していた地図は米国と英国のみ。そこから世界各国に対応していった。当初は「とりあえず作ってはみたが、ろくに(目的地などを)探せないし、経路検索もできない」状態だった。
だが、サービス開始後に衛星写真を表示する「グーグルアース」や街路の様子を画像で示す「ストリートビュー」といった機能を矢継ぎ早に追加。スマートフォンなどモバイル端末への対応も進め、月間10億人以上が利用するツールに育った。
近年は日本でも機能の変更や改修を繰り返す「アジャイル開発」の導入が広がるが、少し前まで高品質の「完成品」を提供することを重視する発想が強かった。変化の速い時代に対応できず、機敏に動く米国勢に後れを取る要因になった。
展開の速さに限らない。エンジニアリングディレクターの今泉竜一氏が指摘するのは「ディスカッションして決断をする過程のスピード感」だ。現場から上がるどのアイデアを生かし、どれを捨てるか。技術を熟知した経営層の素早い判断を強みとしてきた。
もう一つの差は、追い求めるスケールの違いだ。08年にソニーから入社した今泉氏は「技術で世界を良くしよう」という単純だが楽観的なグーグルの考え方に驚きを覚えた。「斜に構えていた昔の自分からすると新鮮だった」と語る。
ふつうの会社員なら現実的に達成できそうな成果を目標にしたくなるところだが、グーグルでは「10%」の増加や改善にとどまらず「10X」(10倍)の革新が奨励される。「できない理由」を並べがちな日本で「世界を変える」と宣言したら笑われかねないが、それを大真面目に追求する姿勢こそが実現へのエンジンとなった。

とはいえ、この20年で社会インフラと例えられるほどに成長したグーグルなど米巨大テック企業には足元で逆風が吹く。プラットフォーマーとして強力な地位を築いたことで独占への批判が高まり、経済格差が広がるなか「稼ぎすぎ」への不満も向けられるようになった。プライバシー保護の要請も強まる。
若かったグーグルも持ち株会社アルファベットの下で約15万人の従業員を抱える「大企業」になり、かつてのように自由には振る舞えない。革新からその後の社会的な要請への対応も含めて、日本企業が学ぶところは多いはずだ。